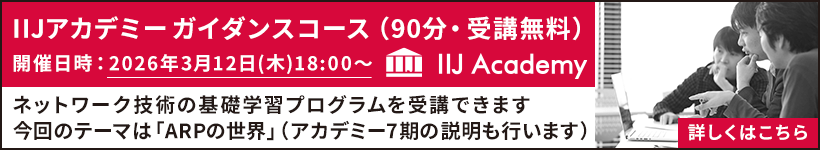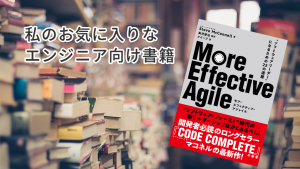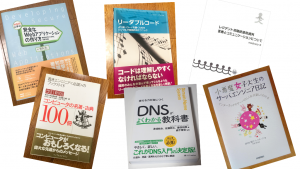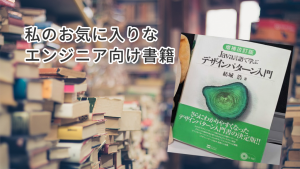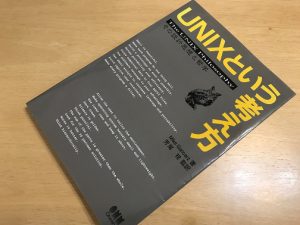IIJの社員が読みたい本ってどんな本(IIJ図書館)
2025年07月07日 月曜日
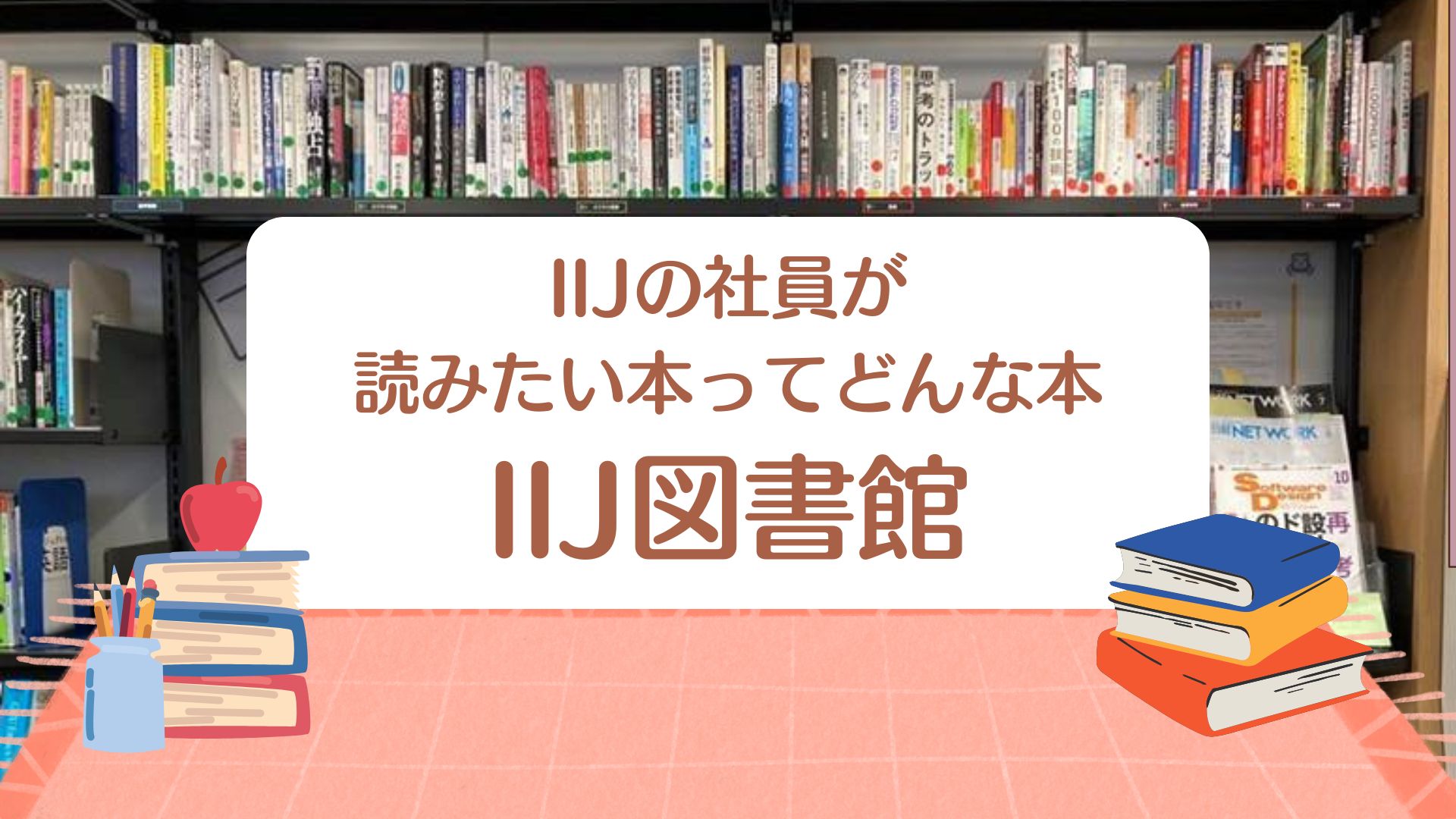
CONTENTS
IIJ社内には、社員が社内で自主的に運用する「IIJ図書館」があります。
IIJ図書館では、置いてほしい本の希望を社内で募り、投票で上位となった本を会社の費用で購入する「みんなの読みたい本を買いましょう」企画を、年に数回実施しています。この企画で自分のオススメ本を挙げた社員に、なぜその本を推したのか理由を聞いてみました。
情シスのIさん『アイディア大全』
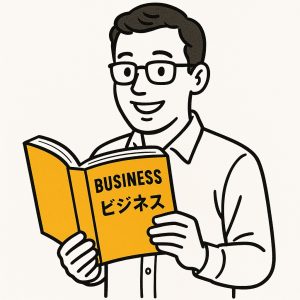
本のURL https://www.amazon.co.jp/dp/4894517450
― 日頃はどんな仕事をしていますか
いわゆる情シスとして日ごろはM365の運用を担当しており、最近ではCopilotの利活用を進めています。社内でM365やCopilotをもっと使ってもらうために、色々な施策を検討しています。
―『アイディア大全』を図書館に推薦したのはなぜですか
チーム内でCopilotのユースケースについて考えていた際に、どこから着手したらいいか質問があったのがきっかけです。アイディアの考え方、アイディアの広げ方についてゼロから考えるのは難しいわけですが、この『アイディア大全』にはゼロからアイディアを集めるためのツールや広げるための方法論がたくさん書かれています。この本があればひとまずアイディアを出す第一歩を踏み出しやすくなるため、課内にもぜひ共有したかったので図書館に推薦しました。
―この本はどんな本でしたか。感想を教えてください。
会社では日々小さな問題、大きな問題が多く発生します。そうした問題に対してちょっとした視点の変え方で面白い解決策が生まれることもあります。日々アイディアについて考えて使いこなしていく習慣を身に着けていくことで、より楽しくやれるのではないかなと思っています。まだまだ自分も本の内容を全部は身につけられてはいないものの、アイディアを出すことについて尻込みせずに向き合えるようになってきました。
クラウド運用のTさん
『よくわかるシステム監査の実務解説(第4版)』
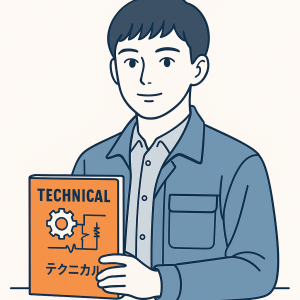
本のURL https://www.amazon.co.jp/dp/4495197843
― 日頃はどんな仕事をしていますか
「IIJ GIOインフラストラクチャーP2 Gen.2」など、IaaSのサービス運用をしています。
―『よくわかるシステム監査の実務解説(第4版)』を図書館に推薦したのはなぜですか
私はサービスの主管部署で働いています。サービス主管自身がシステム監査の視点を持つことは、重大インシデントやセキュリティ事故発生といった有事に備える際に役立ちます。この本は、システム監査に必要なスキルを解説しているので、有事の事前点検に役立ちそうだと考えました。この本の存在は、「システム監査技術者」の資格試験の参考書籍として、とあるブログで紹介されていたことから知りました。
―この本はどんな本でしたか。感想を教えてください。
実は図書館で購入される前に、個人的に購入して読みはじめました。概ね期待通り、役に立つ内容で、特に解説部分や簡易的なチェックリストは、実務に活かせたのでよかったです。また、経済産業省がシステム監査基準やシステム管理基準などのガイドラインを策定し公表しているということをこの本で知りました。IaaSに限らず、サービスを開発・運用する立場の人であれば、この本から品質向上や見落としがちなポイントを見つけるためのヒントが得られると思います。
セキュリティサービス開発のMさん
『情熱プログラマー ソフトウェア開発者の幸せな生き方』
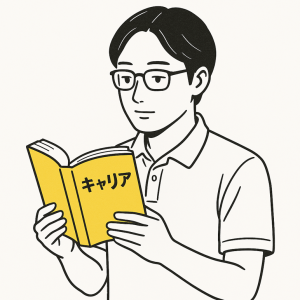
本のURL https://shop.ohmsha.co.jp/shopdetail/000000001848/
― 日頃はどんな仕事をしていますか
セキュリティサービスのエンジニアとして、「IIJセキュアエンドポイントサービス」や「IIJマネージドWAFサービス」の開発に携わっています。また、許可を受けたIIJ顧客からのログ情報を蓄積/解析して、セキュリティ対策などに活用するプロジェクトにも関わっています。
―『情熱プログラマー ソフトウェア開発者の幸せな生き方』を図書館に推薦したのはなぜですか
若手の頃に、ある先輩に紹介されたことでこの本を知りました。以来、仕事がうまくいかない時や、面白くないと感じる時に時々読み返しています。読むと「自分はソフトウェアエンジニアとして、まだまだ未熟だな」と危機感を覚えると同時に、モチベーションが回復する1冊です。新人が入社する時期、この本が図書館にあるとよいと思ったので推薦しました。
―この本はどんな本でしたか。感想を教えてください。
若手時代、別の先輩から「プログラマはカタギではない」と言われたことが、今も強烈に印象に残っています。少々物騒な響きですが、先輩は「ソフトウェアエンジニアは、己の技術一本で組織に貢献する渡世人のような仕事だ、だから常に己の腕を磨いておけ」と言いたかったのでしょう。この本には、己の腕を磨くためのヒントとなる考え方や観点が、53個の章にわたって、ごく読みやすい文体で書かれています。ソフトウェアエンジニアに限らず、己の腕で生きていく仕事であれば、他の職能の人にも当てはまる話が多そうです。
プリセールスエンジニアのXさん
『Azureの知識地図 〜クラウドの基礎から実装・運用管理まで』
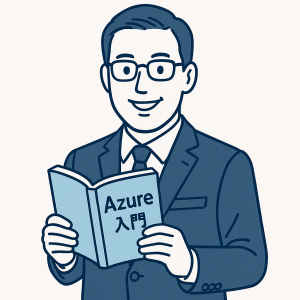
本のURL https://amzn.asia/d/cReevW3
― 日頃はどんな仕事をしていますか
公共系のお客さまに対して、技術的なトピックに関するディスカッションを行ったり、ナレッジ提供をしたりしています。以前、日本マイクロソフトでサポートエンジニアやソリューションアーキテクトとして働いていた経験を活かして、当時の仲間と本書を執筆しました。
―なんと、著者のおひとりでしたか!では著者に直接うかがいますが
『Azureの知識地図 〜クラウドの基礎から実装・運用管理まで』は、どんな本ですか?
この本は、Azureを使いこなすための包括的なガイドとして、初心者からエンタープライズユーザまで幅広く役立つ内容となるよう意識して書きました。マイクロソフトの公式ドキュメントは専門用語が多いなど、初心者には理解しづらい部分があります。この本はそれを補完する役割も果たします。
従来のAzure入門書は、仮想マシンの構築に焦点を当てたものが多いですが、この本はPaaSに重点を置いていて、全体のページ数の半分を占めています。 パブリッククラウドにおいて、サービスの特徴が最もよく現れるのはPaaSだと私は考えます。PaaSは、仮想マシンを立ててシステムを構築する従来の方法よりも、 OS に関わる運用タスクの削減ができる利点があります PaaSを活用すれば、ユーザはインフラストラクチャーの管理に時間を費やすことなく、サービスの構築に集中し、より効率的にアプリケーションを開発・運用することが可能です。
― 仕事で幅広く、そして深くAzureに関わっている人ならではの観点ですね。
技術研究所のSさん
『エンジニアが一生困らないドキュメント作成の基本』

本のURL https://www.socym.co.jp/book/post-19000
― 日頃はどんな仕事をしていますか
社内のイノベーションや組織を超えたコラボレーションの種まき活動として、ワールドカフェ(カフェのようなリラックスした雰囲気で、少人数のグループで自由に意見交換を行い、参加者全体の知識や知恵を共有する対話)の企画・運営を手掛けています。
―『エンジニアが一生困らないドキュメント作成の基本』を、図書館に推薦したのはなぜですか。
かつてSIの現場で、取扱説明書や要件定義書を作成していました。その時、正しく情報を伝えることの重要性を知り、テクニカルライティングに関わる活動を続けています。プログラマやエンジニアにとって、ドキュメントを作成する仕事は、往々にして心理的なハードルが高くなりがちです。しかし、書く際の手順を知っていればそのハードルは下がります。また、手順に沿って書いたドキュメントは、読みやすいものになります。書き手である自分のためにも、読み手のためにもなる1冊として、この本を推薦しました。
―この本はどんな本でしたか。感想を教えてください。
「エンジニアが一生困らない」とポップな印象の題名で、イラストも多めの構成ですが、中身はいたって真面目で、普遍的なドキュメント作成の技術が書かれています。本の帯に「ドキュメントを速く・正確に・わかりやすく書くために必要なのは、まとまった時間じゃなくて手順を知っているかどうかだった」とありますが、本当にその通りです。ドキュメントを書いていて迷ったときに、ヒントを得るため、常に手元に置いておきたい1冊です。
余談
インタビュー中に
「いわゆる自己主張が得意ではない人であっても、自分が好ましいと思うものを他の社員に推薦できる場があることは、ありがたいと思っています」
「他の人が推薦している本を知ることも楽しいので、IIJ図書館の推薦制度はこれからも続けてほしい」
といった言葉を聞くことができました。
ただの本棚にはない、社員が運営する図書館ならではの醍醐味が「みんなの読みたい本を買いましょう」企画にはあると感じました。