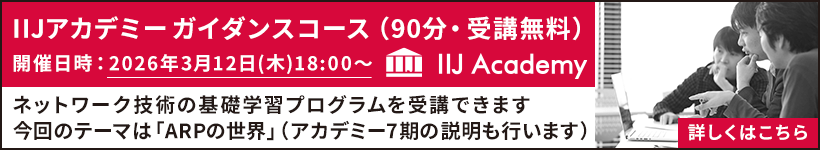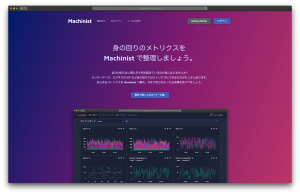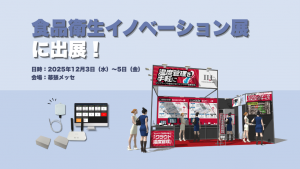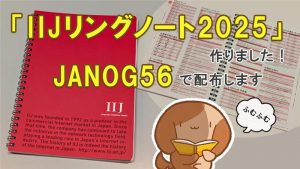GNSS TimeSync 2025の紹介
2025年09月09日 火曜日
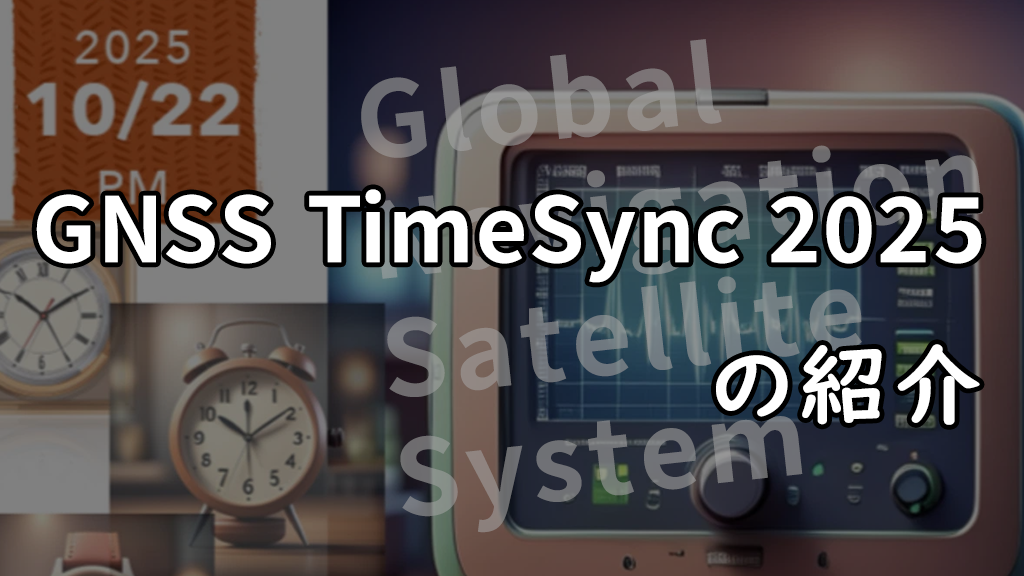
CONTENTS
IIJ放送システム事業部 bunjiです。今回は10月22日にIIJが主催する「GNSS TimeSync 2025」について案内します。
(案内は本記事の最後に記載しているため、先にご覧になりたい方はこちらをクリックしてください)
GNSSとは
“GNSS”とは何か?GNSSは”Global Navigation Satellite System”の略です。地球上空を周回する衛星群(コンステレーションと呼びます)から発信される電波を用い、地表上や上空において受信機から現在地などを割り出すことができるシステムです。日常的にもカーナビやスマホの位置情報サービスで目に触れることが多いでしょう。今どきのクルマにはナビが標準装備されていますが、ナビ普及期には装置を後付けしたことを覚えている方も多いかもしれません。またスマートフォンの位置情報サービスを使ったサービスは圧倒的に便利で、地図を見るだけにとどまらず「近くのお店や駅」などが簡単に探せるようになりました。GNSSは、ITサービスの利便性向上の立役者でもあります。
GNSSは概念を表す言葉です。ちょっと前には”GPS”と言っていたよね?と思われる方もいらっしゃるでしょう。実際にはGPSは米国が運営しているGNSSということになります。他にも何カ国かがGNSSを運用しています。
| 名称 | 正式名称/英文名称 | 運用国 | 衛星投入開始 | 衛星群完成 | 衛星数 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPS | Global Positioning System | 米国 | 1978年 | 1993年 | 約30 |
| GLONASS | Global Navigation Satellite System | ソ連邦〜ロシア | 1982年 | 1995年 | 24 |
| Galileo | EU | 2005年 | 2024年 | 30 | |
| みちびき (QZSS) | 準天頂衛星システム (Quasi-Zenith Satellite System) | 日本 | 2010年 | 2025年度内 | 2025年7月段階で6, 2025年度内に7 |
| 北斗衛星導航系統 | BeiDou Navigation Satellite System | 中国 | 2012年 | 2020年 | 55 |
| NavIC | Navigation with Indian Constellation | インド | 2013年 | 2018年 | 7 |
表1 各国のGNSSの状況
みちびきとNavICは衛星の数が少ないことに気づかれるかもしれません。特定地域向けのシステムのため、全球をカバーするよりも少ない衛星数で構成できます。これらをRNSS(Regional Navigation Satellite System)と呼ぶこともあります。
いずれにせよ一定の国力、より具体的に言えば宇宙開発能力のある国々や連合が運用していることが分かるでしょう。またGPS, GLONASSの運用開始は米ソの冷戦期にあったことも見逃してはなりません。現在地を割り出せることは、軍事行動で非常に重要となるからです。当初GPSは軍事利用に限られて運用されていましたが、1990年代から民間にも開放され、いわゆるデュアルユースとなりました(現在もGPSはアメリカ宇宙軍によって運用されています)。他のGNSSシステムも民間での利用に供されています。
GNSSは位置情報を割り出す用途で多く使われていますが、他にも提供されている機能があり、総合して「PNT」と呼ばれています。
P:Positioning(測位)
N:Navigation(航法)
T:Timing(計時)
航法はすぐに想像がつくと思います。航空機や船舶など、かつては天測等しながら目的地の方角を割り出していたものが、いまや電子的に表示されるようになりました。これが運航の安全に大いに寄与していることは論をまちません。しかしGNSSで「計時」とはどういうことなのでしょうか。
GNSSでの時刻サービス
実はGNSS衛星には高精度の原子時計が搭載されています。その時刻情報は、衛星の軌道情報と共に符号化され、変調され送信されています。受信機では複数の衛星からこれらの情報を得ることで測位できるようになりますが、同時に高精度時刻情報も得られることになります。この精度が何に資するかというと、
- 放送機器の駆動に必要なクロック
- 金融におけるHigh-Frequency Trading
- 電力におけるスマートグリッド
といったことが代表的なものとして挙げられます。GNSSは複数の衛星で構成されていますが(これを衛星コンステレーションといいます)、これはすなわち「どこにいても同じ精度で時刻情報を得ることができる」ことに繋がります。広域化・ネットワーク化された産業システムにおいてGNSSが非常に重要なパーツになることは、簡単に想像ができるでしょう。
| 分野 | 要求される精度の目安 | 用途・背景 |
|---|---|---|
| 電力系統(スマートグリッド、PMU: Phasor Measurement Unit) | ±1 µs(マイクロ秒)程度 | 系統安定化、障害解析、広域監視にGPS同期が使われる |
| 通信(モバイル基地局、5G/6G) | 100 ns ~ 1.5 µs | TDD方式のセル間同期、干渉回避、位置測位補助 |
| 金融取引(証券取引、HFT) | 100 µs ~ 1 ms(規制基準はµsオーダー) | 取引時刻のトレーサビリティ、MiFID II等の規制対応 |
| 放送(テレビ・ラジオ、IP放送) | 1 µs ~ 数 ms | 映像・音声同期、全国放送網の一斉送信制御 |
| 測地・地球科学(GNSS観測網、VLBI) | 1 ns ~ 100 ps | 地殻変動監視、電波干渉測定、宇宙基準とのリンク |
| 産業オートメーション(工場内EtherCAT, TSN) | 100 ns ~ 数 µs | 多軸制御、リアルタイム制御、ロボット協調動作 |
| 鉄道システム(運行制御、CBTC) | 1 ms ~ 10 ms | 運行安全、信号制御、ログの整合性 |
| 航空・宇宙(ADS-B, 航法、深宇宙探査) | 100 ns ~ 数 µs | 航空交通管理、衛星測位、探査機管制 |
| インターネット(NTP, PTP利用) | 数 ms(NTP)、1 µs(PTP/White Rabbit) | 分散システム、クラウド、ログ整合性 |
| 科学実験(粒子加速器、天文観測) | 10 ps ~ 100 ps | LHCなどの衝突実験、干渉計天文学 |
表2 時刻同期精度の要求一覧(例)(chatgpt.comによる)
たとえば放送業界では映像・音声信号のIPネットワーク化に伴い、高精度な時刻情報を共有する必要が生じました。そこでMedia over IPと呼ばれるシステムは、IPネットワーク上でPTP(Precision Time Protocol)によりすべての機器を同期させるデザインが採用されています。このPTPの供給サーバ(Grand Masterと呼ばれます)は、源信としてGNSSが採用されることが多いのです。PTP利用は局舎内にとどまらず、例えば本局と中継車の両方にGNSS源信のPTP GMを配置することにより、離れた場所でも同期が取れるようになりました(実は、今までは同期していなかった)。またラジオ局では音声伝送のためにINSネットが広く使われていました。INSネットでは機器駆動のために網側よりクロックが供給されており、音声伝送機器もこれに従属することで同期が実現できていました。しかしINSネットの廃止や音声信号のIPネットワーク化に伴い、現在ではやはりPTPが広く使われるようになってきています。
NTP(Network Time Protocol)でも源信としてGNSSが採用されることもあります。GNSS受信モジュールがNTPサーバに内蔵され、アンテナ入力端子が付く形になります。なおNTPはPTPよりも時刻精度は緩いため、源信として他の手法(NICTの光テレホンJJYなど)も用いられています。一般ユーザがPCなどの時刻合わせをしたい場合はパブリックなNTPサーバをクライアントとして使うことで問題はないと考えられます。
ところでわたしの家は一般の家庭ですのでGNSSを源信とするStratum 1のNTPサーバが動いており、自宅PCの時刻同期に利用しています。昔々は通信総合研究所(CRL、現NICT)が短波でJJYという標準電波局を運用しており、短波伝搬情報とともに時刻を示すパルスを聞くことができました。5MHz, 8MHz, 10MHz, 15MHzなどよく日がな1日聞いていたものです。JJYはいまは長波で放送されていますが、当方ではおおたかどや山からの40kHzがだいたいSINPO=34433, はがね山からの60kHzがSINPO=24432程度で受信できています(もちろん時間帯によりますが)。なお受信機:Airspy HF+ Discovery アンテナ:15mH YouLoopというシステムです。長波でも案外簡単に受信・復調できて感動しました。ぜひ一般のご家庭でもSDR受信機をおひとつ導入してみてはいかがでしょうか。
閑話休題。
GNSS TimeSyncの課題
このように産業界でも幅広く使われるようになった/なることが期待されているGNSS時刻同期ですが、実はいくつかの課題があります。
受信システムの構築テクニック
現代のITシステムではアベイラビリティの確保が強く求められます。IPネットワークやサーバでは冗長化やクラスタリングなどの技術が幅広く使われており、NTPやPTPでもシステムの冗長化を組むことが可能です。ところが、NTPサーバやPTPグランドマスタの源信側、つまり受信アンテナ側も含めた形での冗長構成をどうやって組めば良いか、悩む方も多いかと思います。また、近年は一般ビルやデータセンターでのGNSS利用も広がってきていますが、アンテナからの配線ルートをどう確保するかも問題になることがあります。GNSSの使用する周波数は1.5GHz/1.2GHz/1.1GHzであり、アンテナから受信機までのルートで減衰しないように太い同軸ケーブルを用いる必要があります。たとえば10D-FBの外径は13mm程度です。このような太い線を縦坑に通すためには十分な空きスペースが必要で、配線自体が困難であることも少なくありません。しかし同軸ケーブルの代わりに電波を光ファイバーで伝達する変換ボックスを用いると、必要なのはシングルモードファイバ1心のみとなり、配線スペースの大幅な削減が可能になります。
ジャミング・スプーフィングに対する対策
近年ジャミング・スプーフィングの問題は深刻になってきています。GNSSに対する妨害の様子を地理的に表わすhttps://gpsjam.org/というサイトが有名ですが、戦争・紛争地域ではGNSSに対する妨害が多発していることがわかります。このサイトは航空機が自機の位置情報などを放送するADS-B(Automatic Dependent Surveillance–Broadcast)の受信データを用い、そのメッセージに内包される航空機上でのGNSS accuracyの情報から、GNSSへの妨害を可視化しています。妨害が行われているエリアは、おそらくミリタリーグレードの電子戦機材による何らかの妨害が実施されているものと思われます。
もちろん、妨害する電波には到達範囲の問題があります。アマチュア無線をやっている方ならマイクロ波での伝搬範囲がどれくらいのものか、想像が付くでしょう。日本で大規模な、つまりミリタリーグレードの妨害を行おうとしても、現実的にはなかなか難しいのではないでしょうか。
…と私もずっと思っていたのですが、2025年の春に東京や大阪の都心で携帯電話が用いる周波数帯への妨害が行われたと知り、震撼しました。報道では「偽基地局」などと報じられていましたが、4G/5Gへのジャミングを実施すると携帯電話端末が2Gにフォールバックする挙動を悪用し、2Gで不法な基地局へと接続させるという仕組みです。携帯電波の世代の差を利用した巧みな攻撃ですが、初手に用いられているのはジャミングでした。単純に元の電波をかき消すだけですので技術的には難しい話ではありません。もし攻撃者側が何らかのメリットを感じるならば、GNSSへの妨害はあり得るのではないでしょうか。
これは、GNSSによる時刻同期を導入しようとするユーザに取って無視できる話ではありません。システム側にどのような対策がなされているか?ユーザ側で対策することはあるのか?そうしたことが課題になっていると感じています。
時刻同期システムの多重化
GNSS時刻同期を受けて動くシステムにとって、レジリエンシは重要なテーマだと思われます。その時、時刻同期をGNSSに頼って良いのか?という議論があるでしょう。
実はGPSのお膝元の米国でも、2020年大統領令13905により「PNTサービスのリスクを洗い出し、重要インフラにおける責任ある利用に移行すべき」ことが示されました(ちなみに、第一次トランプ政権の時です)。その対応として、GPSに依存しない時刻配信サービスの重要性が見出され、政府機関で提案活動が始まっています。
このような動きは英国やスウェーデン、インドでも起きています。いずれにしてもその国における「刻」を管理するのは政府機関ですから、その時刻を使う側との界面には官もしくは官民による時刻配信プラットフォームが必要とされます。時刻同期を受けるシステムを検討する際に、このような動きを押さえておくことは中長期的に非常に重要になるはずです。
GNSS TimeSync 2025への道のり
上記のようなGNSSにまつわる話題を日常的に交わす人たちが、日本にも(少数かもしれませんが)存在します。私は放送分野でのPTP利用という切り口からこのテーマに触れたのですが、販社やベンダーと会話していると非常に面白い。その多くが、業界内部で課題と思っていることがたくさんあるのだが、それがなかなか一般に知られるようになっていないという話でした。こうした話はどんどん広めていかないといけないと感じるようになりました。
また時刻同期にまつわる場にも何度か足を運びました。2024年10月に東京で開催されたIEEEのISPCS(International IEEE Symposium on Precision Clock Synchronization for Measurement, Control, & Communication)や、この何回かのJANOGで開かれているTS-OPS BoFです。これらに参加するうちに、業界横断型のイベントがあると良いと考えるようになりました。
今回のイベントは、業界のかたと電話で会話している時に「あ、イベント成立するかもしれない」と発想を得て、そこから立ち上がったものです。メールを読み返すとその電話は2025年4月3日のことで、少し時間がかかっていますね。ただ人と人の繋がりはとても重要で「あの人を呼ぼう」「あの人にも声をかけなきゃ」という流れが自然にでき、開催にこぎつけることができました。内容についてはかなり煮詰めましたので、面白いイベントになるだろうと思っています。
GNSS TimeSync 2025概要
前置きが非常に長くなりました。GNSS TimeSync 2025のご案内です。
| 日時 | 2025年10月22日(水)14:00 ~18:00(開場:13:30~) |
| 会場 | IIJグループ本社(飯田橋グラン・ブルーム) ※ JR 中央・総武線「飯田橋駅」 西口改札口から、徒歩1分 ※ 東京メトロ 有楽町線「飯田橋駅」/南北線 「飯田橋駅」 神楽坂下方面B2a出口から徒歩2分 本セミナーは「会場参加」または「オンライン参加」をお選びいただけます。 開催前日までにURLを送付いたします。(Web経由で全国どこからでもご視聴いただけます) |
| 参加費 | 無料(事前登録制) |
| 対象 | 分野を問わず時刻同期に関心がある方 |
| 主催 | 株式会社インターネットイニシアティブ |
| 共催 | 株式会社精工技研、セイコーソリューションズ株式会社、古野電気株式会社、丸文株式会社、Calnex Solutions plc、株式会社IIJエンジニアリング |
| URL | https://gnss2025.vidmeet.tv/ |
| 申し込み | https://biz.iij.jp/public/seminar/view/40383 |
ハイブリッド開催となっておりますが、お越しになれる方はぜひ会場においでいただきたいと思います。
GNSS TimeSync 2025は、GNSSによる時刻同期をテーマとし、業界の動向やレジリエントな受信システム、今後の展望について一望できる、日本初の「GNSS時刻同期に特化した技術セミナー」として企画しています。業界の第一人者が、分野を横断しGNSS時刻同期の現在と将来を解説します。以下に講演タイトルを紹介します。
| 時間 | 講演タイトル/話者 |
|---|---|
| 14:00-14:20 |
社会インフラを変えるPTPと時刻同期の進化 セイコーソリューションズ株式会社 戦略ネットワーク本部 戦略ネットワーク営業統括部 タイミングソリューション営業部長 |
| 14:20-15:00 |
GNSSによる高精度時刻同期とその脆弱性対策 古野電気株式会社 システム機器事業部 開発部 主任技師 |
| 15:00-15:30 |
試みてわかる。GNSS受信システム構築の課題とその対策 株式会社精工技研 機器事業部 |
| 15:50-16:30 |
7機体制を迎える準天頂衛星システムみちびき-時刻を提供する社会インフラとしての役割 内閣府 宇宙開発戦略推進事務局 参事官/準天頂衛星システム戦略室長 |
| 16:30-17:10 |
高精度時刻配信の現状と国際動向、NICTの取り組み 国立研究開発法人 情報通信研究機構 電磁波研究所 電磁波標準研究センター 時空標準研究室 室長 |
例えばNTP, PTPなど時刻同期プロトコルに接する技術者に、その前段となるGNSSにまつわる最新の技術動向をお伝えすることが、GNSS TimeSync 2025の狙いです。そのために第一線のメーカや研究機関の技術者・研究者をお招きし、講演いたします。放送・通信・金融を含め、時刻同期技術に関心のある方全てが参加対象です。
株式会社インターネットイニシアティブ、株式会社精工技研、セイコーソリューションズ株式会社、古野電気株式会社、丸文株式会社、Calnex Solutions plc、株式会社IIJエンジニアリングによる展示ブースを設けております。また内閣府、NICTのコーナーも用意します。早めに会場にお越しになり、疑問や質問があればぜひ直接話をしてみてください。
GNSS TimeSync 2025が目指すもの
GNSSによる時刻同期に特化したイベントというのは、国内では初めての開催なのではないかと考えています。(先行するイベントがありましたら訂正します……)ラインナップの特徴としては、産官とり混ぜてのセミナーとなっており、さまざまな角度から時刻同期についての話題がお届けできると思っています。まさに2025年の今でこそ語れる・お伝えできる内容ではないでしょうか。
こうした会合やコミュニティの創生というのも、今回のイベントを契機にして考えていきたいです。産官のチャンネルも必要ですし、産業界でも業態をまたいだ情報交換は今後さらに必要性が増していくと考えています。そもそも今回IIJは主催の立場で動いていますが、講演する予定はありませんでした。これも、コミュニティに対する貢献として捉えていただければと思います。私もIIJに長くおりますが、IP技術とは直接関係のない、話題の中心ではないセミナーを主催するようになるとは思ってもみないことでした。
ぜひ、こうした「試み」に対して反応をお寄せいただきたいと考えています。このような情報交換の場が必要であることは間違いありません。継続した活動が求められているかどうかも含め、皆さんからどのような反響をいただけるか関係者一同楽しみにしております。
関連リンク
なぜIIJがこういったセミナーを開催しようと思ったのか、セミナーの見どころも紹介したブログも公開しています。
- GNSS時刻同期の最前線を体感!「GNSS TimeSync 2025」開催決定
https://note.com/iij_live/n/n872d036a8621