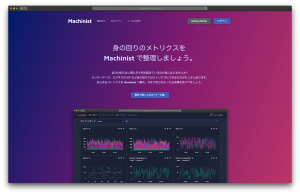千葉県白井市の田んぼでのIoTセンサーを活用した獣害対策実証 ~人と動物が共生する地域づくりを目指して~
2025年08月04日 月曜日

CONTENTS
有害鳥獣による被害の状況
IIJのアグリ事業推進部では、スマート農業の推進を全国で92地区で支援をしています。
水田の水位・水温を測定する「水田センサー MITSUHA LP-01」をはじめ、露地栽培やハウス栽培で利用する環境モニタリング・土壌・気象・水利施設監視・わなセンサーなどのIoTデバイスを駆使し、地域の課題解決のお手伝いをしています。また、これまで農業関連の現場で培ってきた屋外IoT技術やデータ解析等について日々、現場での実装検証を重ねて改良をしています。
こうしたスマート農業の現場での取り組みの様子は、IIJ Engineers Blogでも随時ご紹介していますので、ぜひご覧ください。
今回は、農業現場における「獣害対策」にフォーカスし、IIJの「白井データセンターキャンパス」がある千葉県白井市でのわなセンサーの実証についてご紹介します。
日本における有害鳥獣(イノシシ、シカ、ハクビシン、アライグマ等)による農作物被害は深刻で、特に北海道ではその被害額が大きく、令和5年度には農業・林業・水産業全体で63億6千9百万円に達しました。センサー等をつかって収量を上げるより、有効な獣害対策を行うほうが簡単に収量が上がるという声もあります。
有害鳥獣による被害が年々増えていますが、猟友会の会員は高齢化や会員が減少しており、対策に頭を悩ませている自治体や農家さんが多い状況です。
千葉県白井市での農業IoTを活用した獣害対策実証
これまで千葉県白井市の田んぼでは、他社機器とのシステム連携や、様々なLPWA通信規格(Low Power Wide Area:低消費電力で広範囲なエリアをカバーできる無線通信技術)のフィールド試験、水田センサーを活用した水管理の実証などを進めており、昨年のノベルティで配布した白井市の「IIJ IoT米」はIIJ社員が田植えからセンサーを活用しての水管理、稲刈りまで行いました。
くわしくは、過去の投稿の「IIJ IoTチーム スマートファーマーに転生!?」「IIJ IoT米、2024年も作りました!」をご参照ください!
今年度はさらに取り組みの幅を広げ、田んぼ付近の「獣害対策」に取り組んでいます。今回の「獣害対策」は、白井市における環境保護活動の一環として始まったもので、外来種や有害鳥獣の生態を正しく把握しながら、人と動物が共に暮らせる地域づくりを目指しています。有害鳥獣をただ駆除すればよいわけではないのです。
実証で利用したわなセンサー
今回、設置するわなセンサーは過去に「振動検知 + わな作動検知センサー」として山陰地区で実証実験をしていました。柵に取り付けて、動物にアタックされた柵の場所を振動で特定する想定でしたが、風雨等のノイズによる誤検知が多いため、振動検知機能をなくして「わな作動検知センサー」単体として改良したセンサーです。
わなセンサーを利用することで、猟師さんがわな見回りの回数を減らしたり、わなが作動していれば捕獲の準備をして現場に向かうことができます。
わなセンサーの多くは、磁石を使ったドアの開閉センサーを屋外で利用できるようにカスタマイズしたものです。駅などの個室トイレの利用状況をお知らせする仕組みに使われているあれです。屋外でわなセンサーとして利用するには防水機能の他に、わなが作動した際、ワイヤーとつながった磁石がなくなることが多かったのでメーカと連携して対策を行いました。

エルスピーナヴェインズ社のわなセンサー
わなの作動を検知するわなセンサーは箱わな、くくりわな、囲いわななどに後付で設置できます。
写真は今回、白井市に設置した箱わなとセンサーは同様で、展示用に箱わなにセンサーを取り付けています。箱わなの中にいるのは北海道のお土産として有名な「シャケをくわえたクマ」で、「ケンゴ」と名付けて展示会で活躍しています。

箱わなに取り付けたわなセンサーのイメージ
わなセンサーの設置
白井市産業振興課の方と相談をして、田んぼ近くにいるであろうアライグマの捕獲を想定し、地元猟友会の方にご同席・アドバイスをいただきながら、わなセンサーの設置をしました。

箱わなの設置場所を決める
実際の設置作業の様子を、写真や映像とともにご紹介します。
獣道になっている場所を見つけ、付近にわなセンサーを仕掛けます。

左側の写真から獣道がどこだかわかりますか?
箱わなを設置する
白井市では箱わなの貸出をおこなっており、アライグマを捕獲するために利用する箱わなを貸出をしていただきました。
箱わな設置場所付近に金属や人のにおいが残っていると、動物が警戒して近づいてこないため、箱わなを一度水でしっかりと洗ってから使用します。
箱わなを設置する向きですが、山へ戻るときにアライグマが入るように、斜面の下側に入口を向けます。また、獣道上に設置してしまうと動物が警戒して近づかなくなってしまうとのことで、箱わなは獣道から少し横にずらした位置に設置しました。

わなセンサーの取り付け
動物が箱わなの中に入り、中にある踏み板を踏むと、蓋が閉まることでワイヤでつながったセンサー部分の磁石がはずれ、スマホアプリ「MITSUHA」に通知が届きます。
通知によって捕獲対象外の動物がかかっていた場合でも(錯誤捕獲といい、速やかに放獣する必要がある)、見回りに行くより早く対応ができるため、動物にやさしい仕組みになっています。
展示用では箱わなにわなセンサー本体を直接取り付けていますが、捕獲された動物によって通信ケーブルを噛みちぎられたりする可能性があるため、わなセンサー本体は近くの木に設置しました。ワイヤーの長さによって磁石部分がうまくはずれなかったため、長さを調節しました。こういったフィールド試験で得られた知見はわなセンサーの設置マニュアルに反映しました。

実際にわなが動作するデモの様子がこちらです↓
エサを箱わなの中に置く
初回のエサはドッグフードをネットに入れて使用しました。ネットに入れたのは、動物が匂いで誘われるのと、エサ交換が楽にできるようにとの工夫です。
エサを踏み板の奥において数日間様子をみていましたが、箱わなのなかまでは動物が入る様子がないため、箱わなの入口付近にもエサをおいてみました。結果、入口付近のエサだけ食べられて、箱わなの中にあるエサは手つかずでした。
白井市産業振興課の職員さんと連携をして、エサの定期交換の際にお菓子などに変えて様子をみています。人間と動物の知恵比べです。

スマホアプリ「MITSUHA」の通知
水田センサー、土壌水分センサー、環境モニタリングセンサー等の測定値や、データ分析結果を確認できるスマホアプリ「MITSUHA」でわなセンサーの動作状況・検知通知が確認できます。
「作動後経過時間」は、わなセンサーが検知してからの経過時間を確認することでき、見回り頻度のエビデンスにも活用できます。
また、わなセンサーの動作状況確認のため、3時間に1回動作状況を定期的に通知する仕組みを入れました。

スマホアプリ 「MITSUHA」のわなセンサーの表示画面
トレイルカメラによる撮影
箱わなの様子がわかるように、トレイルカメラも設置しました。
トレイルカメラは周辺で人や動物の動きを検知すると自動的に撮影する仕組みになっており、わなセンサーの通知が来たときに、どのような動物がかかったのかを確認することができます。

匂いにつられて近くに来たアライグマが、トレイルカメラについている赤外線センサーが反応して写真が取れました。

ほかにもネコやアナグマも来ていました。ネコは捕獲対象外なので、錯誤捕獲した場合は速やかに放獣する必要があります。

さいごに
獣被害対策のフィールド試験にご協力いただいた地元猟友会の方、農家さん、そして白井市産業振興課の皆様へ、この場をお借りして心より感謝申し上げます。
私事ですが、狩猟のことをもっと詳しく知ろう!ということで2024年にわな免許を取得しましたが、実践する機会がなかったので今回はとても良い経験になりました。
人と動物が共存していくためにも、生態を正しく知ることはとても大切です。
IIJでは製品やアプリを効果的に活用するために、フィールド試験を通じて製品の改良やアプリの改修を行っています。
今後もアグリ事業推進部では白井市をはじめとする日本各地での経験、利用者の意見をもとに、日本のスマート農業の発展に貢献していきますので引き続き応援をよろしくお願いいたします。