IIJ IoTチーム スマートファーマーに転生!?~白井圃場で水田センサー・自動給水装置を設置してみた~
2024年06月11日 火曜日

CONTENTS
こんにちは、IIJ の IoT事業部でスマート農業を推進している花屋です。
さて、IIJではIoTを活用したスマート農業に力を入れていることを本ブログファンの皆さんはよくご存じではないでしょうか。
そう、「IIJのIoT米」「スマート農業の授業」「DIYで気象センサー設置」「発育指数(DVI)がつなぐ水稲栽培の未来」など投稿しています。
いろいろなスマート農業の取組をしてきましたが、最近いよいよメンバーのスマート農業熱が高まった結果、実は自分たちでも圃場に稲を植えたり、田んぼに水田センサーを設置したり、自分たちで田んぼの水管理をアプリでやってみたり、とても楽しいことになっています。
今日はそんなIIJ IoTチームの水田水管理について熱い活動をお伝えしていきます。
取り組みの目的と背景
5/30に、「IIJ、千葉県白井市の圃場でスマート農業の実証実験を実施」と題してプレスリリースを出しました。
プレスリリースで発表した「稲作でいろいろなIoTデバイスをテストしたり、LoRaWANⓇ、Private LoRa、Wi-Fi HaLow™などのテストをする」ことも重要ですが、「農家さんがどんな苦労をしているか体験する」ことも取り組みの目的の1つです。
|
「自分たちでスマート農業やってみた」 目的
|
|---|
|
① IIJメンバーが水田センサーで水管理・水位管理をやって農業を知りたい ② IIJはLoRaWANⓇを使っているけれど、ほくつうさんはPrivate LoRaを利用されていて、どのように連携できるか試したい ③ 田んぼのCO2を抑制し、抑制したCO2をIIJの白井データセンターに活用できるか模索 (カーボンクレジット) |

こんなことやってみた
いろんなことをやっているため、今回は簡単に概要だけ紹介します。
1.代かき (しろかき)
- 田植えの前に行う準備で、田んぼに水を入れて、土を均等にしていく作業です。 稲をしっかりと育てるためにとても大事な作業です。
- IIJメンバーが操作するため、農家さんからトラクター操作の指南を受けています。

2.田植え
- IIJメンバーみんなで田植えをやってみました。苗の積み込みは肉体労働でとっても重い!

- 田んぼはでこぼこしていて、田植え機をまっすぐ走らせるのは難しい。

- さすが農業初心者たち、どうやらうまくいっていなかった箇所もチラホラ・・・

3.水田センサー設置
- 「水田センサーの設置はもう手慣れたもの!?」と思ったけれど、やはり改めて設置してみると新たに気づくことも多々ありました。(次章でご紹介)

4.水管理
- 自動給水装置 paditch gate (笑農和)と水まわりくん(ほくつう)を水田センサーと連動したり、リモートで操作して水管理。IIJメンバーが水抜けに合わせて給水を行いますが、天気によりポンプ場が動いていないことも。
- 木枠を作成して設置したpaditch gate。

- ほくつうの水まわりくん。IIJメンバーが北海道や静岡に出張中でもリモート操作可能です。

気づきと鉄則
気づきと鉄則 その1: 水田センサーの設置場所は超重要、水流の気持ちを察すべし
水田センサーを設置する時、「水流がある場所には水田センサーの設置を避けてもらう」という注意点を案内しています。
今回の水田センサー設置で、自動給水装置の近くのゆるやかに水流がある場所に水田センサーを設置してみたのですが、それでも水流の影響で水位がバタついてしまいました。
他にも、風の影響で田んぼの風上と風下で水位が変わったりすることなど、現場でいざ設置して水管理をしてみると気がつくことが沢山あるのが分かります。
ホント、やってみてよかったです。

気づきと鉄則 その2: 機器の扱いはやっぱり現場感が大事、回数こなしてコツをつかむべし
今までも何度となくやって来たはずの水田センサー設置・・・でも、引っかかるポイントがありました。
田んぼへ設置する前に水田センサーの通信ボックス部分の蓋を開けて作業をしていたのですが、その時に蓋を十分に閉め忘れていました。蓋を閉めるための目印は付けてあるのですが、「もう少し目立つようにしないと」と気がつきました。

また、水田センサーの設置方法を十分に理解していないIIJメンバーが、水田センサーを設置する時にパイプのジョイント部分を打ち込んでパイプの中に入ってしまったりと失敗ポイントがあるので、なるべくシンプル化や注意書きをわかりやすくして失敗を防ぐ方法も考える必要があります。今後の取説やマニュアル動画にどう反映しようか、そんなことを考えるきっかけになりました。

他にも沢山の気づきがあるのですが、長くなってしまうのでまずはこれまで。
好評だったら是非シリーズ化したいテーマです。
今後にこうご期待!
まずはどんな想いでやっているか、どんなことをやっているか、を簡単にご紹介してみましたが、どうでしたでしょうか?
より現場感を持って水田水管理をしていく
「水田センサー+自動給水装置」ってことは、自動給水は全自動でもできます。
でも、自動にできるけどやっていません。
田んぼの管理を「自分ごと」にしていきたいので「今のタイミングかな!?」と思ったタイミングで、敢えてIIJチームメンバーが手動でリモート給水調整をしています。
もっともっと「農家さんがどんな苦労をしているか知る」ためにも沢山の経験をしていきたいと思います。
白井市にご恩返しをしていく
本取組みに快く承諾をいただいた白井市と田んぼを貸してくださった白井市の農家さんに感謝しております。
しろいまっちでも、こんな風に紹介されていますね。市内の水田で「スマート農業」実現化へ向け、実証実験が始まりました!
今回、冒頭でご紹介したプレスリリースでも「白井市産業振興課と協力し、これらの分野においてもスマート農業による課題解決」とありますが、白井市の実証を通じて、日本の農業の発展につなげていくので応援をお願いします。


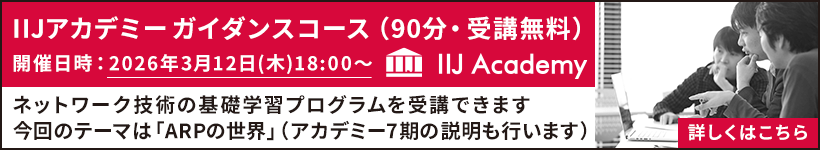



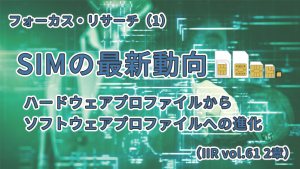
![「Network Stomper開発 Project 基板設計記[第2回(全5回)]」のイメージ](https://eng-blog.iij.ad.jp/wp-content/uploads/2019/10/da0d64e8fa9d6b228262cf9e9903cb6b-300x169.png)